AMP & LEAP
ここで得た知識と繋がりがプロジェクトを成功へ導く
AMP:知識や繋がりを増幅させる
LEAP:業務やプロジェクトを大きく飛躍させる

ここで得た知識と繋がりがプロジェクトを成功へ導く
AMP:知識や繋がりを増幅させる
LEAP:業務やプロジェクトを大きく飛躍させる
ワークショップ内容を公開しました
タイムスケジュールを公開しました
イベントサイトを公開しました
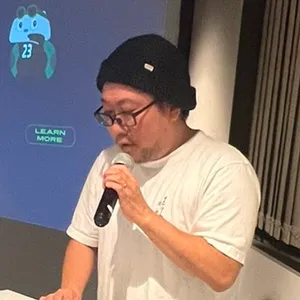
実行委員長
Katsuge Tetsuya
メディア総研株式会社
高専生・理工系学生の採用支援会社でマーケティングを担当。Backlog Worldは2023年と2024年の2年間、実行委員として運営に携わりました。コミュニティから生まれる出会いが好きなので、JBUG福岡やその他のコミュニティイベントも運営しています。
※タイムスケジュールは予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
| Aホール | Bホール |
|---|---|
| - 受付 | |
| - 開会式 | |
| - # 公募セッション 生成AIでBacklogの活動履歴を宝の山に変える方法 株式会社デジタルキューブ岡本 秀高 | - # ワークショップ 課題って、どう切ってる? — みんなで考える“課題の切り方”ワークショップ Backlog World 2025 実行委員 |
| - # 公募セッション 「やり方」より「やる人」──プロジェクトを進めるBacklog活用の現実解 株式会社JBN金子 大地 | |
| - # 公募セッション プロジェクトマネジメントからプロダクトマネジメントへ:価値中心のアプローチで実現するアジャイルなプロダクト開発 クリエーションライン株式会社中村 知成 | |
| - 昼休憩 | |
| - # 基調講演 生成AI時代のチーム設計 ― 役割と協働の再構築 株式会社アトラクタ吉羽 龍太郎 | |
| - # 招待講演 事業部のプロジェクト進行と開発チームの改善の “時間軸” のすり合わせ 株式会社Kyashこにふぁー | - # ヌーラボ推薦枠 「AIに任せたいなら、まずBacklogに書こう!」— 情報を残す文化がチームを強くする — 株式会社ヌーラボ河野 千里 |
| - # プラチナスポンサー たくさんの高専生が参加するイベントの運営を入社一年目の私が主担当としてチームを機能させたBacklog活用術 メディア総研株式会社與那嶺 円 | |
| - # プラチナスポンサー 抜け漏れは努力でなく、仕組みでなくす〜SalesforceとBacklogがつなぐ業務の自動化〜 株式会社フライク新堀 立樹 | |
| - Good Project Award 2025 審査 | |
| - # 招待講演 翻訳・対話・越境で強いチームワークを作ろう! 株式会社LayerX新多 真琴(あらたま) | - # 招待講演 エンジニアのためのドキュメント力基礎講座〜構造化思考から始めよう〜 ARアドバンストテクノロジ株式会社中野 康雄 |
| - # ゴールドスポンサー Backlogで未来のプロジェクトをPlayしてみた話 株式会社TAM中村 颯介 | |
| - # ゴールドスポンサー 運用をデザインする — Backlogで“人に寄り添う仕組み”をつくる 株式会社ビーワークス漆迫 雅充 | |
| - JBUG表彰式 | |
| - # 招待講演 正確なタスクを積み上げてプロジェクトを成功させる - 生成AI 時代にも通じる基本中の基本 パラダイスウェア株式会社橋本 将功 | - # ヌーラボ推薦枠 管理者に向けた1クリックBacklog 〜ドキュメント機能を用いたBacklog文化の浸透〜 北海道ガス株式会社峠 幸寛 |
| - # ヌーラボ推薦枠 AIとナレッジ共有で進化するBacklogの未来 株式会社ヌーラボ吉澤 毅 | |
| - # 招待講演 杜甫々がプロジェクト管理で実践していた小ネタいろいろ 「とほほのWWW入門」サイト管理者杜甫々(とほほ) | - # 招待講演 プロジェクトマネジメントの歴史的変遷と新たな潮流 広島修道大学経済科学部教授佐藤 達男 |
| - Good Project Award 2025 発表 | |
| - 閉会式 |
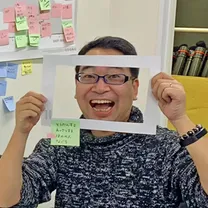
Yoshiba Ryutaro
株式会社アトラクタ Founder兼CTO/アジャイルコーチ
Scrum Alliance認定スクラムトレーナー(CST)。Microsoft MVP。 野村総合研究所、Amazon Web Servicesなどを経て現職。 アジャイル開発、DevOps、組織開発を中心としたコンサルティングやトレーニングが専門。 著書に『SCRUM BOOT CAMP THE BOOK』(翔泳社)など、訳書に『ダイナミックリチーミング』『Tidy First』『プロダクトマネージャーのしごと』『エンジニアリングマネージャーのしごと』、『チームトポロジー』(日本能率協会マネジメントセンター)など多数。
生成AIは、私たちの働き方だけでなく「チームのつくり方」そのものを変えています。これまで専門性ごとに役割を分けてきたチーム構造も、AIが一部の作業を担えるようになったことで見直しが必要になっています。

Arata Makoto
株式会社LayerX バクラク事業部エンジニアリングマネージャー
ソフトウェアエンジニアとしてキャリアをスタートし、前職では執行役員CTOを務めた。現在はLayerXにて「バクラク申請・経費精算」のEMを担いつつ、コミュニティ「EMゆるミートアップ」、カンファレンス「EMConf JP」を運営している。著書に「エンジニアリングマネージャーお悩み相談室 日々の課題を解決するための17のアドバイス」。
私は、チームで課題に取り組むことが好きです。そして、よいチームワークが「1+1=∞」な成果につながる瞬間が大好きです。プロジェクトを成果へとつなげるには、メンバー同士の専門領域をうまく織り合わせることが必要不可欠。それぞれの目線を借りながら、課題の本質を炙り出し、意思決定を行うために土台となるのがチームワークです。本セッションでは、このチームワークを築くためのちょっとしたコツを、翻訳・対話・越境の3テーマに分けてお話しします。

konifar
株式会社Kyash 執行役員 VP of Engineering
ワークスアプリケーションズ、奇兵隊、Quipper Limited. を経て、2017年Kyash入社。 AndroidやiOS開発を経験した後に、2019年からMobileチームのEMを経てサーバーサイド、QAチームのEMも担いました。 2021年にEMロールから離れ、QAチームのいちメンバーとしてテストの自動化を半年ほど手がけた後に、2022年よりVPoEとして開発チーム全体のマネジメントをしています。 2024年より執行役員として経営に携わり、日々がんばっています。
事業計画から逆算されて取り組むプロジェクトは完遂させたい。一方で、開発チーム内で取り組むべき改善も進めていきたい。どうしても短期的にはプロジェクトを優先するという意思決定をしがちですが、それが続くと中長期的な改善はまったく手がつけられなくなってしまいます。プロジェクト進行と開発チームの改善の "時間軸" の違いを組織全体で認識し、どうすり合わせていくか、具体事例を元に話していきます。プロジェクトも守る、改善もする、両方やらなくっちゃあならないってのが面白くもあり辛くもあるところです。覚悟はいいか?オレはできてる
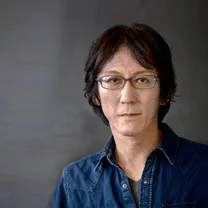
Sato Tatsuo
広島修道大学経済科学部教授
プロジェクトマネジメントが普及し始めた1990年代から、SIerで数多くの情報システム開発プロジェクトのPMを務めた後、全社のプロジェクトを統括するプロジェクトマネジメント部長を経て、2016年より大学で「プロジェクトマネジメント論」を講義。日本プロジェクトマネジメント協会理事、PMI日本フォーラム2019基調講演、主な著書「プロジェクトマネージャ育成法」、「改訂4版P2M標準ガイドブック」(改訂委員・執筆)、ハーバードビジネスレビューのプロジェクトマネジメント特集号(2025年8月)にインタビュー記事「次世代プロジェクトマネジメント」掲載。
プロジェクトマネジメントは、20世紀のはじめに近代マネジメントが誕生して進化していく過程で、機能別部門組織による伝統的なマネジメントでは成功に導くことが難しい大きな問題、非日常的な問題、部門横断的な問題などに対応する新しいマネジメント方法論として登場しました。本発表では、世界的な影響力をもつ米国のプロジェクト、プログラムマネジメントの歴史的変遷を概観し、近年はアジャイルなどが広く浸透する中で大きな転機を迎えたプロジェクトマネジメントとプログラムマネジメントの新たな潮流について論じたいと思います。
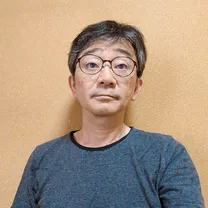
Tohoho
「とほほのWWW入門」サイト管理者
1988年大学卒業後メーカー系IT関連会社に入社。 1996年から個人活動としてWebに関わる技術情報の発信サイト「とほほのWWW入門」を運営してきました。HTML/JavaScript/CSS、各種プログラミング言語、フレームワークなどの入門情報を発信しています。 最近はWeb技術もネタが尽きてきて陶磁器、洋楽、中国語、韓国語、タイ料理など様々な「○○入門」の発信に手を出しつつあります。今回は「マネジメント」がテーマとのことで、会社の開発チームで実践していた子ネタ群をいくつか紹介してみたいと思います。
「とほほのWWW入門」は個人の活動ですが、本職のソフトウェア開発で実践していたプロジェクトの管理に関わる小ネタをいろいろ紹介してみようと思います。プロジェクトフォルダ構成、仕様書の書き方、プログラミングスキルの見える化などなど。

Nakano Yasuo
ARアドバンストテクノロジ株式会社 取締役執行役員
1999年フューチャーアーキテクト株式会社に入社。2009年より株式会社ディー・エヌ・エーにてECマーケットプレイス事業のサービス企画と開発マネジメントを担当。その後コーチング事業での独立を経て、2012年より現職。現在はBXD第2事業ドメインを管掌し、マネジメント業務の傍らPJ実務にも複数関与。IT全社戦略策定や内製化支援、システム提案や上流工程、プロジェクトマネジメントに関して多くの経験を持つ。
サイト制作やシステム開発の現場では、実装よりも“要求や仕様の記述”に時間がかかります。AI時代になってもこの事実は変わりません。むしろ、AIに正しく読み解かせ、人と合意形成するための「漏れなく・誤解なく・素早く伝える」力が武器になります。本講演では、ドキュメント作成の土台となる構造化思考を、実例と短い演習を交えて徹底的に解説します。

Hashimoto Masayoshi
パラダイスウェア株式会社 代表取締役
パラダイスウェア株式会社 代表取締役 早稲田大学第一文学部卒業。文学修士(MA)。IT業界25年目、PM歴24年目、経営歴15年目、父親歴11年目。 Webサイト/ Webツール/業務システム/アプリ/ 組織改革など、500件以上のプロジェクトのリードとサポートを実施。世界のプロジェクト成功率を上げて人類の幸福度を最大化することが人生のミッション。 著書に『人が壊れるマネジメント』(2025, ソシム)『プロジェクトマネジメントの本物の実力がつく本』(2023, 翔泳社)『プロジェクトマネジメントの基本が全部わかる本』(2022, 翔泳社)。
プロジェクトの失敗は、実はタスクの積み上げ方に大きな原因が潜んでいます。『人が壊れるマネジメント』で描いた“壊れる理由”を出発点に、タスクをどう定義すれば人を守り成果につなげることができるのかをお話します。鍵となるのは RQ-AC-DD というシンプルな型。生成AI が普及する時代だからこそ、タスクの基本を忠実に実行することが新しい武器になります。本セッションでは、その実践の考え方と持ち帰れるチェックリストをご紹介します。

Nakamura Tomonari
クリエーションライン株式会社 Agile CoE アジャイルコーチ / スクラムマスター
新卒でSIerに入社後、ヌーラボに転職。Backlogの開発・運用を担当しつつ、CI/CDなどの取り組みも行う。その後、チーム作りや改善活動の難しさ・楽しさを実感し、アジャイルを突き詰める活動を始める。現在は、クリエーションラインでスクラムマスター・アジャイルコーチとして、チーム・ユーザーともに喜びを届ける活動に従事している。書籍:SCRUMMASTER THE BOOKの共同翻訳者
従来のプロジェクトマネジメントは、「予め定めたゴールの達成」を目的とし、期限・予算・スコープ・品質などの管理に焦点を当てています。一方、現代の不確実・複雑な状況下では、定められたものを作っても、それが価値を生み出すかは分かりません。そのため、「価値の最大化」を目指した継続的な活動を行っていく、プロダクトマネジメントも意識する必要があります。 本セッションでは、プロダクトマネジメントにおける価値中心のアプローチを紹介します。価値に密接に関係する「アウトプット・アウトカム・インパクト」の概念から、アウトカムを可視化するための手法や、スクラムでいうプロダクトバックログに落とし込む流れを、活用事例やBacklogでの実現方法例を踏まえながら解説します。

Kaneko Daichi
株式会社JBN
Web制作会社ディレクター兼チームリーダー。ディレクター歴6年目。証券会社、広告企画会社での営業経験を経て現職。長野県長野市在住。1992年生まれ。Backlog利用歴6年。好きな機能はガントチャート。2024年に「JBUG Creative」を立ち上げ。Mr.Childrenと星野源をよく聴くリトルトゥース。
プロジェクトを円滑に進めるためには、ツールの機能や設定はもちろん重要です。しかし地方では紙依存を始めとした非効率なプロジェクト管理が蔓延する中で、その力を最大限に発揮できるかどうかは、実はクライアント側のプレイヤー(旗振り役)をどう選ぶか、つくるかが重要です。Backlog活用も例外ではありません。 どれだけ使いやすいタスク管理機能やコミュニケーションの仕組みが揃っていても、クライアント側にそれを主体的に運用し、チームを巻き込める“プレイヤー”がいなければ、機能は使われずプロジェクトも前進しません。 本セッションでは、現場のリアルな事例を交えながら「機能を活かすための人づくり・人選」という視点から、Backlogが活きる環境をどう作るかを解説します。プロジェクトの成否を左右するプレイヤーの重要性とその関わらせ方について、現実的かつ実務に直結するヒントをお届けします。

Okamoto Hidetaka
株式会社デジタルキューブ
DigitalCubeのBizDev。EC ASPの開発やStripeのDeveloper Advocateとしての経験を元に、SaaSやECサイトの収益を増やすための方法・生成AIを使った効率化や新しい事業モデルの模索などに挑戦する。
生成AIの登場で、ナレッジや対応履歴などの記録やドキュメントを残すことの重要性が高まっています。「XXさんに聞かないとわからない。対応ログが見つけられない」「Yさんが知ってるはずだけど、今移動中だから連絡がつかない」「議論が長くなってきて、結局何をすればいいかわからない」のような困り事を経験したことはありませんか?これらは全て履歴を正しく残すこととナレッジとして検索可能な形に保存することで解決できます。
しかし社内ナレッジベースは多くの場合廃墟になりがちです。欲しい情報が見つからない見つからないから情報を追加しない情報が古くなって余計に使われない・・・こんな苦い経験をされたことのある方も少なくないでしょう。
DigitalCubeでは、社内文化として履歴をほぼ全てBacklogに記録しています。しかしやはり情報の検索性・ナレッジベースのさらなる利活用には課題があり、「XXさんに聞かないとわからない」という状況は残っていました。そこで2025年から新しい取り組みとして、全社員にBacklogやesa / Webサイトの情報を検索・取得できるMCPサーバーの提供を開始しました。なぜMCPサーバーなのか、導入によって変わったことがあるのか、どのような点に注意をしているか。など、この半年強での試行錯誤をお話しします。

Tohge Yukihiro
北海道ガス株式会社
新潟で育ち、大学進学を機に北海道へ。澄んだ空気で長年の鼻炎が治り、永住を決意。都市ガス会社に入社し、電力自由化では夢だった“ガス会社での発電所建設”を担当。次の挑戦を求め、2018年にIoT・クラウドを学ぶ社内有志コミュニティを立ち上げる。活動範囲を社外コミュニティへ広げ、JBUGやBacklog World2023で事例登壇。2024年以降のBacklogWorldの運営に携わる。基幹システム刷新プロジェクトに従事し、社内のBacklog浸透にも力を注ぐ。
管理者は「全体計画や進捗」を、担当者は「具体的なタスクや制約、目的」を重視するため、確認したい情報の粒度が根本的に異なります。さらにボトムアップでBacklogを導入すると、担当者が日常的に利用する一方で、管理者は操作に慣れるまでにどうしてもハードルが生じやすいのが現実です。本発表では、この二つの課題に対して、“ドキュメント機能“と“種別設定“を工夫して解決した内容となります。ドキュメント上に、管理者専用の進捗確認ページを1枚用意し、そこから各チームのガントチャートへワンクリックで飛べるように設計し、管理者は余計な操作をせずとも全体進捗を俯瞰できる環境を提供し、その上で、使い慣れるにつれて自ら検索やフィルター操作を試すようになり、ツール利用の定着が自然に進みました。管理者は会議中の入力に追われる場面が減り、進捗差異やリスク等の重要トピックに多くの時間を割けるように会議が変化。管理者・担当者双方にとって効率的な進捗共有環境を実現した事例を紹介します。

Yoshizawa Tsuyoshi
株式会社ヌーラボ
2009 年にヌーラボへプログラマーとして入社。受託開発を経て、「Backlog」「Cacoo」の開発や「Typetalk」の立ち上げを行う。2024 年からは Backlog のプロダクトマネージャーとして開発全般を統括し、より多くの人の働きを支えるサービスづくりに取り組んでいる。Backlog スター機能のプロトタイプ開発者でもある。
AI アシスタントやドキュメント機能など新たな進化を遂げるBacklogが、チームの協働・意思決定・成長をどう支援していくのか。現在開発中の新機能を紹介しながら、Backlogの今後の展望についてお話しします。

Kouno Chisato
株式会社ヌーラボ
システム開発の現場で顧客課題の解決に取り組み、チームをより良く機能させるためにBacklogやCacooを活用してきた。ユーザーとしての試行錯誤を糧に視野を広げ、 2025年4月に株式会社ヌーラボにエバンジェリストとしてJOIN。現場でのリアルな経験をもとに「チームワークマネジメント」をベースとしたチームでの協働をもっと心地よく、楽しくするためのヒントや工夫を伝えている。
AIに仕事を任せる時代だからこそ、チームが「書く文化」を持つことが重要です。タスク、議論、判断のプロセスをBacklogに記録することは、単なる作業ログではなく、チームの知恵をストックし次の意思決定を助ける“チームワークマネジメント”そのもの。しかし現場では、「書く時間がない」「どこに書けばいいかわからない」といった“Backlogあるある”が、情報の断絶を生みがちです。本セッションでは、ヌーラボが考える“情報を残すチーム”のあり方をお話しいたします。
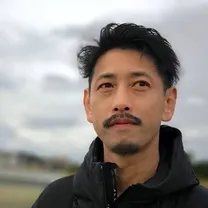
Kaneuchi Toru
合同会社CGFMUIデザイン伴走アドバイザー
JBUG福岡vol.0から参加。元フロントエンドエンジニア。現在はUIデザイナーとしてWebサービスや業務特化型SaaSの設計に携わりつつ、事業会社のUIチーム育成や、利用者視点のデザイン文化づくりを支援。企業・自治体・大学で「身体知」を大切にしたワークショップを100回以上実施。皆さんと楽しく悩み、対話しながら“あ、そんな考え方もあるんだ”と思える場にできたら嬉しいです。
日々の業務やプロジェクトで直面する「課題」。その「課題の切り方」に悩んだことはありませんか?課題の粒度、マイルストーン、カテゴリや種別の使い分けなど、「どう設定すればいいのかわからない…」という方も多いはずです。
このワークショップでは、“課題の切り方”をテーマに、参加者同士で語り合いながらヒントを見つけていきます。Backlogユーザー同士が、楽しく悩み、対話する場を通して「そんな考え方もあるんだ」という視点を持ち帰ってもらえたら嬉しいです。

株式会社フライクは、SalesforceやBacklogを中心にシステムを組み立て、業務フロー設計から導入・伴走支援まで一気通貫で提供。SaaS研究と設計書品質にこだわり、企業の成長を支援する唯一無二のパートナーです。

全国でも珍しい高専・理工系大学生専門の就職活動支援・キャリア⽀援に取り組む会社です。高専生のみを対象としたセミナーや合同説明会、技術系企業と全国の理工系学生が一堂に会する企業研究イベントの開催に加えて、情報ナビサイト「高専プラス」やパンフレットなどの制作までワンストップで手がけてきました。高専・理工系大学生採用のノウハウを活かし、サイトや動画といった企業の採用活動コンテンツ制作も行なっています。

2001年創業、200名規模の総合デザイン会社です。Web制作・出版サービス・自社ゲーム開発など、幅広い事業を展開しています。クライアントワークにおいては、課題の本質を見極め、ブランディング・UX/UI設計からアウトプットの制作まで、工程・媒体を問わないデザインを通して課題解決をサポートしています。また、自社ゲームブランド BEEWORKS GAMESの代表作『なめこ栽培キット』シリーズは、全世界累計6,000万ダウンロードを突破し、10年以上にわたり多くのファンに親しまれています。
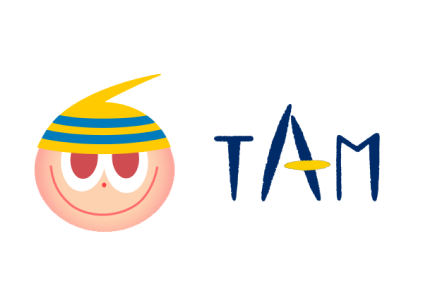
TAM(タム)はお客さまと共に新しい価値を共創するクリエイティブな開発パートナーです。コンサルティングから、制作・開発、マーケティング、現場運用まで伴走します。ユーザー体験の重要性が認識され、「経営にデザインを」と叫ばれる今だからこそ。ビジネスの成果を目指すのは当然のこと、私たちTAMは専門家として、アイデアとデザイン、それを社会に実装する技術にこだわります。
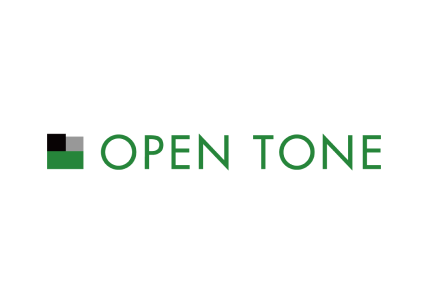
オープントーンは『まだないものをまだ届かないところへ』をコンセプトに最先端のIT技術により生み出したアプリケーションをビジネスの現場や社会に送り届けています。また、Backlogの公式パートナーとして、導入支援や業務改善のコンサルティングを行うBacklog助っ人サービスを提供。Backlogを中心としたサービスの活用支援とプロダクト開発を通じ、お客様の課題解決に貢献します。
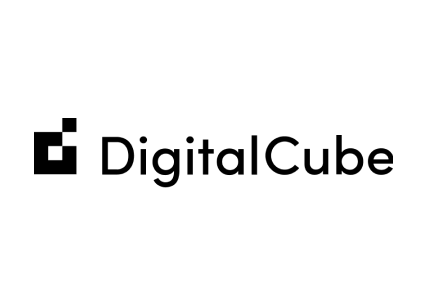
株式会社デジタルキューブは、2006年の創業以来、WordPressという世界標準のプラットフォームを軸に事業を展開しています。オープンソースとクラウドを組み合わせることで、新しい価値の創造に取り組んできました。「Amimoto」や「Shifter」といったWebホスティングに関する自社プロダクトの開発・運用を通じて、大手企業からスタートアップまで、業種・業界を問わず多くのクライアントとの協業実績があります。また、神戸本社をはじめ、東京、宮城、香川に拠点があるほか、従業員やパートナーが全国各地にいる強みを活かし、地域課題の解決や地方間でのシナジー創出にも積極的に取り組んでいます。
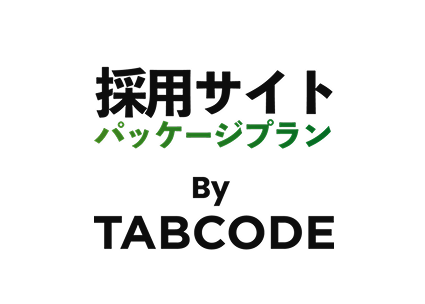
ウェブの技術や考え方は、次々と新しいものが生まれ、刻々と状況が変わっていきます。その中で、予算規模、ターゲットユーザーなど、お客さまが置かれている条件はさまざま。「これをやれば大丈夫」という単純な答えは存在せず、新しい技術を使うのが正解とも限りません。弊社は「どんな施策・技術がお客さまの今の状況に合うか」を考えることを大切にしています。
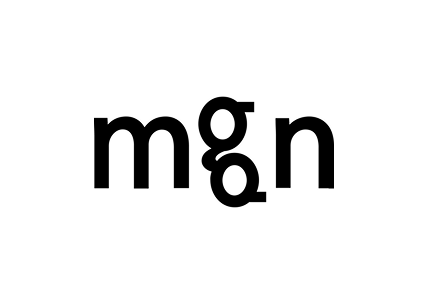
私たちはお客様のビジネス発展に貢献するWebサイトの企画、制作、運用サポートを行ってます。WordPressをはじめ、サイト制作について専門的に取り扱ってますが、Webサイト以外も含め、お客様のビジネスの「本当のゴール」に近づくための道を考え、ゴールにたどり着ける提案をいたします。私たちは、お客様に寄り添い、最適なWeb施策を実現する伴走者となることを目指してます。

株式会社エコンテは、「世の中の"いいコト"を、わかりやすく伝える」を企業理念に掲げるコンテンツマーケティング専門会社です。デジタル領域にとどまらない幅広いソリューションを通じて、お客様の「いい想い」を伝えるコンテンツを提供。インフォグラフィック、ホワイトペーパー、動画制作、オウンドメディア構築などの多彩なサービスで、企業のブランディング強化や集客力向上を支援しています。

GitHubやJiraなどの開発データを解析し、生産性と開発者の体験、ツール導入の投資効果を可視化する「Findy Team+」を提供。Four Keysなどの開発アクティビティや開発者体験データを自動で可視化し、チームの課題発見・改善を支援します。またAI支援で組織のボトルネックを特定し、AI導入の効果測定や戦略的意思決定までサポートします。

サムライズムは国内トップクラスのソフトウェアソリューション提供経験を活かしデベロッパ向けツールの開発・販売・サポートやトレーニングの提供をしております。主にソフトウェア開発者向けのツールを取り扱っておりJetBrains、GitHubなど海外のトップベンダとパートナーシップを提携しております。

ネクスキャット株式会社は、デザイン組織構築を推進するクリエイティブパートナーです。より多くの企業が自らの創造力を発揮し、価値を社会に届けられるように、フルスタックデザイナーの定額サービス Desinare(デジナレ) を中心とした、企業のデザイン組織に必要なリソースの提供や内製化支援を行っています。

ジョイゾーはkintone専業のSI企業として豊富な実績を持ち、CyPN Reportで4年連続星を獲得。2時間×3回の打ち合わせで行う定額制対面開発「システム39」は累計1,750件超を対応し、多様な業種の業務改善を支援してきました。さらにプラグインや自治体特化パッケージ「ジチタイ39」など、kintoneを軸に幅広いサービスを展開しています。

「Spice up your life」をスローガンに、社会を豊かにするサービスやデザインに挑戦しています。ブランディングやウェブサイトの企画・開発を手掛け、Backlogでのプロジェクト管理を実践。ヌーラボ公式パートナーとして導入支援や運用アドバイス、セミナーも行っています。

株式会社ネクストスカイは、企業のDXを実装力で前進させるシステムインテグレーターです。小さく速く試し、確実に伸ばす——機動力と意思決定の速さで、顧客の事業成果にこだわります。

自社サービス、受託サービスのマーケティングやコンサルティングの仕事をしています。LT会を主催したり参加したりもしています。使っているプロジェクト管理ツールはBacklog、好きな乗り物はバイク。好きな動物はネコです!
紆余曲折を経てJBUG岡山の二代目運営です。岡山のいろいろなソフトウェア開発者向けコミュニティの運営に関わるCEO(Chief Enkai Ojisan)。ハードコア麻婆豆腐に定評があります。
北海道十勝出身のエセ浜っ子で宇宙好き。パシフィコ横浜にて新規事業や地域連携業務を中心に、ITを活用した課題解決に注力したり。Backlogには何度も危機を救われ、人生預けたレベルで活用しています。
ガス会社なのに発電所設計、続いてDX部署にてプロマネ担当!Backlog World2023 初登壇、2024は初運営にてワークショップを担当!今年もワークショップやりまっせ!趣味はクラフトビールとサウナとLT!
ご縁があってはじめてBacklog Worldに関わらせていただきます!普段はフリーランスとして色々な企業の仕事をお手伝いしつつ、犬2匹とのんびり暮らしています。おいしい料理とお酒を持ってキャンプに行くのが好きです。よろしくお願いします!

JBUG名古屋運営。Backlog利用歴約15年。2023年12月に東京→愛知にUターン。フルリモートでEMをやっている、5児のパパエンジニアです。Gallup認定ストレングスコーチとしての活動も行っています。
Web制作会社向けの「JBUG Creative」運営。北海道出身、千葉県在住。株式会社プロクモの執行役員兼クリエイティブチームマネジャー。BacklogWorld2024に登壇、今年は運営として参加させていただきます!
ヌーラボ所属。島根県の西端からフルリモートで働くエンジニア。PjM, PMOとして世界中のメンバーと協力しながらヌーラボのサービス開発を進めている。Backlog World 2021運営委員長。
教育業界で大手進学塾の情報システム部門にて十数年。社内基幹システムの開発保守における開発ベンダーやエンドユーザーとの調整、プロジェクトマネジメント、内部統制(IT統制)の構築を担当し、当時の東証一部上場達成に貢献。21年からはワイン専門商社にフィールドを移し、同じく情報システム部門のIT Support & Strategyとして会社全体のIT管理、PJ管理、DX推進に従事。
Backlog歴3年目のWebデザイナーです。Backlog World 初参加・初運営で、デザインを担当しました!兵庫県に住んでいて、美味しいご飯を食べることが生きがいです。
